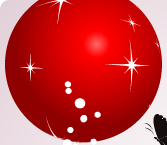1
神田が高校3年に進学して、1ヶ月が経った。だからと言って、神田の生活が変わるわけでもない。
毎朝、近所をジョギングした後、誰よりも早く登校して剣道の自主練習をする。授業を受けて、休み時間は基本的に1人で過ごすが、たまにラビが絡んでくるので無視をする。放課後は誰よりも遅くまで部活動。大体いつも8時頃に寮に帰る。
神田の通う、聖十字架学園は付属大学までエスカレート制なので、受験勉強に追われることもない。冬に行われる進学テストにさえ受かれば大学に進むことができる。勉強量を増やすのは、部活動を引退する秋頃からで充分だと、神田は思っている。
なんにしろ、神田はこれまでと同じように学校生活を送っていた。
だが、たったひとつ、変わったことがあった。
しかし、ささいな変化など、神田にとって何の影響もない。
そう思っていたのだが……。
「ユウ~!今日も蕎麦ってるかあ?」
「……うるさいぞ、食事中だ」
「蕎麦って、おいしいですよね」
「…………」
「俺はラーメンのが好きだけどな~」
聖十字架学園名物のハンバーガーが乗ったトレイを置いたラビの隣に、中等部の制服を着た少年が両手にいくつもトレイを持って立っている。
これが、今年になって神田の周りに起きた変化だった。
この春に中等部に編入してきた注目の生徒、アレン・ウォーカーが、なぜか高等部のラビとつるむようになり、そこからイモヅル式に神田の周りをうろつくようになったのだ。
神田自身は気付いていないが、神田はこの聖十字架学園で最も目立った存在だ。美しく冷たい容姿、所属している剣道部では学園でも群を抜いて最強の腕の持ち主であり、すぐにキレる凶暴な性格の一匹狼。男女関係なく、神田のファンは学園中に溢れている。
そして、その神田に臆することなく話しかける唯一の生徒、ラビもまた、学園内では目立つ存在だった。神田のようにファンクラブができるようなことはないが、いつも明るく笑い、誰でも気軽に話しかける性格で、高等部中等部に関わりなく、ラビには友達が大勢いる。
それゆえ、今までも神田とラビのペアは(ラビの一方的な友情だとしても)学園内では注目を集める組み合わせだった。
そこにアレンが加わって、他の生徒にとって彼らは聖十字架学園黄金トリオのような存在になっていた。
アレンは、この春中等部3年に編入してきた。
非常に優秀な成績で編入試験に合格したことで入学前から噂になっていたのだが、さらに彼は容姿も可愛らしく、誰にでも柔らかな笑顔で接し、心地の良い敬語で話すことで1ヶ月足らずで学園中にファンを持つようになった。
今やこの学園は、神田派とアレン派に分かれていると言っても過言ではない。
氷のように冷たく美しい神田。
可憐な花のように可愛らしい、アレン。
だが、そのような派閥ができていようと、本人たちはどこ吹く風。神田に至ってはそのような学園の状況にも気付いていないが、彼らがどう思っていようと、3人は現在、この学園で最も熱い存在だった。
そんなわけで、今、彼らは学食内の視線を一挙に集めていた。
あまりにも注目すると神田がキレるので、生徒たちは関心がないフリをしつつ、全神経を集中させて彼らに注目している。「黄金トリオが学食にいるぞ!」というメールが飛び交っていることも本人たちは知らない。学食は中等部、高等部、大学部共通の大きな施設なだけに情報はまさに学園中駆け巡ることになる。
そんなとてつもなく大きな変化が起こっているが、神田にとってそれは何の問題でもない。彼自身が、そんな学園の状態に気付いていないのだから。
神田が意識している変化。それは。
アレン・ウォーカーの存在そのものだった。
アレンは両手に持ったトレイをテーブルに置くと、ラビの隣に腰を下ろした。神田、ラビ、アレンと並んで座る格好になる。
神田はアレンが置いたトレイをチラリと横目で見た。相変わらずの量だ。
ハンバーグやらスパゲティやらピザやら、カロリーの高そうなメニューで、軽く10人前はある。アレンは、その小さな身体に毎食ありえない量の食事を取るのだ。
毎食。
神田がそれを知る程に、アレンはしょちゅう神田と同じテーブルで食事を取っていた。
寮での夕食も、アレンはラビと共に神田に付きまとってくる。
1人を好む神田としてはとても鬱陶しいのだが、追い払うのも面倒なので無視していた。だが、こうも毎日毎日付きまとわれていると、ストレスが溜まる。
そういえば、アレンが来るまでは、ラビもこうも毎日神田に構ってくることはなかった。
「神田はよっぽど蕎麦が好きなんですね。学食以外でもおいしい店とかご存知なんですか?」
非の打ち所のない笑顔のアレンが、穏やかに話しかけてきた。
「あ、俺もそれ聞きたいさ!ていうか今度連れて行ってくれよ!」
ラビも便乗して身を乗り出してくる。
「……ねえよ。あってもお前らには教えねえ」
「ええ~?なんでさ?けちけちすんなよ~」
「僕はこの町に引っ越してきて間もないですから、オススメのお店があれば教えてほしかったんですけど……」
「そうだよな~そろそろいろいろ案内してやりたいよな!」
神田が喋らずとも、2人は勝手に盛り上がる。
2人は必ず神田が食事をしている最中に来るので、神田は食べ終わるまで席を立てない。なので、邪魔くさいのだが、食事が終わるまでは2人が横に座っている状態で数分を過ごすことになる。
最初は話しかけられても無視をしていたのだが、特にラビはしつこい。話しかけられればとりあえず返事をするが、2人と会話をする気は神田にはない。
必ず食事中を狙って隣に座るのもまた、アレンが来てからだ。
なぜこの2人がつるむようになったのか、聞いてもいないのにラビが話してきたことがある。
アレンは編入時にかなり注目されていたというのは、神田もラビから聞いて一応は知っていた。なので、当然面白がったラビからアレンに話しかけたのだろうと思っていたのだが、そうではなかったらしい。
さすがのラビもアレンに興味はあったものの、新学期早々中等部まで足を運ぶヒマをなかなか得ることができずにいた。
そのラビに、アレンから話しかけたらしいのだ。
放課後、1人で学園を見て回っていたアレンが、高等部校舎に迷い込んでしまった。
辺りも暗くなってゆく時刻、校内に他生徒をみつけることができずに困っていたアレンだが、誰もいない教室で、放課後歴史に関する書物を読みふける習慣があるラビに偶然出会い、その日一緒に寮に帰ったらしい。
それが縁になって、高等部中等部の境界を越えた友情が生まれたのだ。
それからというもの、ラビとアレンは毎日必ず食事は一緒に取っているし、登下校も一緒なことが多いようだ。
そんなわけで、自然に神田の側にアレンがいる時間も長くなった。
いつもラビも一緒にいて、ラビはアレンを可愛い可愛いと、弟のように接している。
「ごちそうさまでした」空になった皿を重ねて、アレンは手を合わせた。重ねた皿は大小合わせて20枚ほど。
「相変わらずすげえ食うなあアレンは…それでそんなに痩せてるんだから不思議さ」
「毎日バイトに明け暮れてますから。体力の源のご飯はいくら食べても足りないんですよ」
呆れたように言うラビにアレンは笑う。
するとそこに、みたらし団子が載った皿を持った女子生徒が数人、アレンの横に立った。
「あの、アレンくん……これ、調理実習で作ったお団子なんだけど、どうかな?アレンくん、みたらし団子好きよね?」
高等部の制服だ。名札の色から、2年生だと知れる。彼女たちは各々、自分の作った団子を持っている。
学食中の生徒がアレンを見た。
座ったまま彼女たちを見上げていたアレンが、おもむろに立った。
そして、天使のような顔で笑った。
「いいんですか?ありがとうございます。どれもとてもおいしそうです。皆さん、お料理上手なんですね」
そして、先頭に立つ少女の皿から団子を1本取り上げると、ぱくっと口に入れ
「おいしいです」
と背後に花が咲き誇るような笑みを浮かべた。
きゃああ、と少女達から黄色い悲鳴が上がる。
「アレンくん、わたしのお団子もどうぞ!」
「わたしも、アレンくん好みの味にしたのよ!」
アレンは、1人ひとりに笑顔で接し、団子を食べては賛辞を返している。
「アレンってすげえなあ……入学早々すげえ人気だよな~……」
あれだけの量の食事を食べた上に30本以上の団子をにこにこと食べているアレンを呆然と見つめながら、ラビ。
「でも、あんな風においしいって感激してもらえたら、女の子達も嬉しいよな」
とてもおいしいです。
ありがとうございます。
全員に完璧な笑顔で接するアレン。
神田は、その様子を横目でチラリと見、箸を置いた。
「アレンはほんとに女受けがいいよな。特に年上。俺も綺麗なねえちゃんゲットしたいんだよな~。ユウもアレンの半分くらいは愛想よくしてもいいんじゃねえ?」
神田は、トレイを持って立ち上がった。
「作り笑いのプロかよ。ご苦労なこった」
「え?」
なにか言ったか?と言うラビを無視して、神田は学食を後にした。
これだけ毎日毎日側にこられれば、客観的にアレンを見る自分は嫌でも気付く。
そんなどうでもいいことに気付いてしまった自分に苛つく。
そして、そんなことで苛つく自分にも腹が立つ。
アレンは、誰に対しても愛想がいいが。
奴は、1度だって本当に笑ってはいない。
--END--