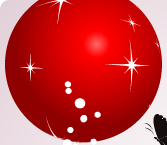「I wish…」
「こんなに古い日本的な家だと、アレンジするのが楽しいわね」「せっかく工房を構えるんだ、ご近所を驚かせるくらいでないとな」
背中から聞こえる両親のはしゃいだ声を、夏野は冷めた気分で聞いていた。
(……ふざけんなよ)
「夏野くん、どっか行くの?」
玄関の戸を開ける寸前、目ざとく母親に見つかってしまい、軽く舌打ちをする。できるなら気付かれずに家を出たかった。
小さい子供みたいに苛ついている顔を見せるのは、癪だ。
「ちょっとその辺歩いてきてみるよ」
夏野は振り返らずに玄関を開けた。古い家屋は建付けが悪く、ガラガラと耳障りな音を立てる。それがいっそう夏野を苛つかせた。
追うように父親の
「近くに何があるのかチェックしてきてくれ」
という声が聞こえたが、言われた内容があまりに馬鹿らしかったので、適当に手を挙げて応えた。
(……なにもあるはずが、ないじゃないか)
夏野一家は、今日、昨日まで住んでいた街からこの村に越してきた。
外場村。
人口の少ない、いかにも閉ざされた風情の、暗い村だ。
初めてこの村を見た時の印象は、檻のようだと思った。
四方を山と道路で囲まれた、閉鎖的な村。そして実際に入ってみれば、閉鎖しているのは外見だけでなく、村そのものだと分かった。
実際、こうして夏野が家から出ると、刺すような視線が追いかけてくる。それは道なりに建った家の窓からであり、物陰からであり、あからさまな好奇心の色、そして余所者を排斥するかのような色を帯びていた。
これからしばらくは珍獣扱いを受けるのは間違いない。夏野を見た村人がひそひそと何かを囁き合うのも気に食わなかった。
(……こんな田舎……)
煩わしい視線を避けるように歩いていると、やがて日が暮れてきた。気がつくと夏野は、今朝タクシーで通ってきたばかりの国道に出ていた。
この国道をずっと歩いていけば、あの街に帰れる。
そもそも、15年間都会で暮らしてきた、自分のような若者が、両親の勝手な都合で(……逃避で)こんな田舎に連れて来られて、不満に思わない訳がない。
それを理解できない両親に、腹が立つ。
だからといって、素直に面と向かって文句を言えないだけのプライドを持つ自分にも腹が立った。子供のようにいやだいやだと駄々をこねるようなみっともない真似は、したくない。
だが、そんな無駄なプライドは捨てるべきだったと、夏野はさっそく後悔の念を覚えていた。
この国道の向こうに、自分の居場所が。
しかしそこは、あまりにも遠い。
電車さえないこの村。まるで鎖で拘束されるように。
焦がれるように国道に見入っていると、近くで小銭が落ちる、澄んだ音がした。
追うように、若い男の軽い声。
「お。と、と」
ちらりと足元を見ると、100円玉が1枚、足元に転がっていた。夏野がそれを拾い上げて顔を上げると、20歳ほどの若い男が微笑んで手を出してきた。
「サンキュ」
どこかほっとするような、明るい笑顔をした青年だった。
■
「見ない顔だと思ったらやっぱり今日越してきたとこか」
青年はちょっと話をしないか、と言って、国道沿いにあるドライブインの自販機でジュースを買ってきた。そのまま2人で国道のガードレールに寄りかかっている。
話さないか、と言われた時に、ああ質問攻めに遭うのか、と思ったにも関わらず断ることができなかったのは、この青年の出すやわらかく、安心感のある雰囲気のせいだろうか。
武藤徹、19歳。
年齢より落ち着いて見えるのは、田舎育ちで自立しているせい、そして高校を出た今年の春から会社勤めをしているせいだろう。
相手が夏野に興味津々なのは当然のこと、しかし夏野もこの徹に少しなりとも興味を持ったのもまた事実だ。
「結城夏野くん?」
ふいに名前を呼ばれて夏野は驚いて徹を見た。その様子に徹も慌てたように
「あれ?やっぱり小出の方だったか?」
と言った。夏野は更に驚く。
「どっちも正解だけど。……なんで名前、知ってんの」
徹は悪びれもしない顔で笑った。
「田舎の情報網を侮ったら駄目だぜ。1回下見に来たろ。その段階でじいさんばあさんが我先にと情報を集め始めるんだよ」
「…………」
想像以上の田舎の恐ろしさに、夏野は深く項垂れた。プライベートはどこにいったのだろう。つうかプライベートって言葉をここの住人は知ってるのか?
「……ろくでもないな」
「ん?」
「あんたもよくこんなとこ住んでられるよな。働いてるんならいつでも出て行けるだろ?電車がないなんて考えられねえ。田舎すぎるよ、ここ」
その言葉に徹が軽く目を見開く。しまった、つい言い過ぎたかな、という思いが夏野の胸を掠めた時、ふいに徹がくくく、と笑いだした。
「違いないな」
夏野はなんとなくバツが悪くなって徹から目を逸らした。自分らしくない、相手のペースにはまりそうだ。
ちらりと目を向けると、笑いながら座り込んだ徹が涙目で笑いながら自分を見上げていた。
「まあでも、そんな田舎でもなんかいいこともあるかもしれないぜ」
こんな出会いとか。
「どーだか」
夏野は、ぐいとジュースを飲み干した。腰を上げると、徹が隣を歩いた。
「今度うちに遊びに来いよ。うちの弟、お前と年近いぜ。美人の妹もいるし」
こんな村に住むなんて、とんでもない。
でもこの出会いは、悪くない。
そう思っている自分も、悪くない。そう思った。
--END--