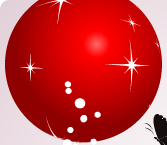2
神田が毎朝何時に寮を出て、何時までジョギングをして、何時に一度寮に戻り、何時に学校に向かうのかも、アレンは知っている。神田の好きな食べ物も、神田の私服が何着あるのかも、神田が今読んでいる本のタイトルも、神田の毎日の授業の時間割も、得意な科目も苦手な科目も、知っている。
神田がどんな字を書いていて、授業中のノートを意外と几帳面に書いていることも、知ってる。
休み時間をどう過ごしているのか、特に嫌いな教師は誰なのか。
そんな些細なことでも、神田のことを知ることは至福の喜びだった。
この学園に編入してよかった。
今までは調べるにも限界があったことまで、知ることができる。
それがごくつまらないことであればあるほど、アレンは喜びを覚えた。
これらは、すべて自分で調べたことだ。
神田はこの学園でかなりの人気があり、単なる好奇心のふりをして他の生徒に神田のことを尋ねたことがある。この学園に編入して間もない頃のことだ。 神田がこの学園内でアイドル的存在であることはアレンも承知していたが、その時その現実と共に、抑えきれない衝動を突きつけられた。
生徒たちは、神田のことをよく知っていた。
この学園は小学部からのエスカレート制。アレンのように編入してくる生徒も少なければ、転校してゆく生徒も少ない。それはつまり、この学園の生徒は、小学生の頃から毎日を共に過ごしていることになる。
他の生徒たちは、アレンが神田の存在を知る遥か昔から神田を知っていて、神田と同じ時間を共有していた。そしてそのことを、無邪気にアレンに話すのだ。
アレンは、自分の中に嫉妬の炎が燃え上がるのを感じた。
目の前のこの生徒の脳を喰らえば、彼の記憶が自分のものにならないだろうかと、本気で考えたこともある。
今では、その衝動もチリチリと胸の中で音を立てる程度に抑えることができるようになったが、悔しさは拭えない。自分が知ることのできない神田の姿が、他人の中にあることが許せないと思う。
それならば、他の誰も知らない神田を自分のものにしたい。
神田の過去が手に入らないのであれば、未来は自分のものだ。
手に入れて、他の誰の手にも届かないところに、閉じ込めてしまいたい。
ラビの存在を知ったのは、そんな風に、他生徒に神田のことを聞いていた時だ。
神田は登下校どちらもいつも1人だったし、校外で誰かに会っていることもないということは知っていたので、一匹狼タイプなのだということは知っていた。だが、そんな神田に臆なく接する存在がいることは、知らなかった。
アレンにとって、学園にひしめく神田ファンの面々など、敵ではなかった。現に、すでに自分に乗り換えている生徒が半数。残りの神田派の生徒達も、放っておいても問題はなさそうではあるし、いざとなれば潰せばいい。
だが、既に神田に近しい存在がいるというのは、聞き捨てならないことだった。
そのラビという生徒も目立つ存在のようで、少し好奇心をちらつかせれば、ラビの情報も色々と手に入った。
ラビは、毎日放課後7時頃まで、教室で本を読みふける習慣があるらしい。
アレンは、それを利用してラビと接触しようと試みた。
どういうつもりで神田に絡んでいるのか。
返答次第では、まずラビを潰さねばならない。
そう思って近づいたラビは、予想に反して、実にあっけらかんとした性格をしていて、そのようでとても繊細で、人の気持ちを正しく読む人間で、とても素直だった。
人間の暗い部分もきちんと承知しているのに素直。人を楽しませるのが好き。神田の人嫌いをきちんと把握しながら、神田の内面もしっかりと捉えていて、その上で神田に興味を持って神田と話をする。
その行為はなにも裏がなくて、そのまっすぐな人柄に、アレンも引き込まれた。
ああ、可愛い人だ。
ラビはアレンを可愛い可愛いと言い、それからもちょくちょく話しかけるきっかけを作れば心底嬉しそうに接してきた。それでも、なぜこの学園に編入してきたのかや、家族構成など、踏み込んだことには決して踏み込まないところが心地よかった。
ああ、この人はよく分かっている。
これはいくら神田に絡んでいようと放っておいても大丈夫。それどころか、利用しない手はない。
それと同時に、このあたたかい人の側にいたいとさえ感じるようになった。そう……ラビは、マナを思い出させる。安心できる他人だ。
ラビと親しくなれば、神田に近づくことは簡単だった。ほんの2、3日、昼食時に神田に話しかける習慣をつければ、自然と毎日神田に話しかけるおうになる、あとは、その時間をアレンが誘導すれば、ごく自然に神田の近くに座ることができた。
他にも、ラビを間に挟めば、寮のなかでも神田に近づく時間を増やすことができた。
神田は、ミーハーに話しかけられれば無視をするか、怒鳴りつけるが、穏やかに話しかけられると、戸惑う傾向がある。
そして、毎日同じタイミングで話しかければ、さすがの神田も自分の生活の変化を意識し始める。それはつまりアレンを意識し始めているということだ。
少しずつ神田の中に入っていく。
そうして、神田の中をアレンでいっぱいにするのだ。
早朝の、凛とした空気が好きだ。
天気がいい日ならなおのこと、雨が降っていても、それはそれで早朝の湿った空気が神田は好きだった。
早朝は人がいないのもいい。大抵の人間はまだ夢の中で、街中にいつものような喧騒がないところが、一番気に入っている。
誰にも邪魔をされることなく、何も考えずにただ前だけを見据えて走るこの時間が、神田にとって1日の中で一番大切にしている時間かもしれなかった。 雨が降っていれば、学校の道場で精神統一。誰もいない、がらんとした道場も好きだ。空気が冷たく、自分がそこに座ることで、張り詰めると、より気が引き締まった。
今日は、雨が降っている。
神田は布団から起き上がると、窓を開けた。
人嫌いの神田の部屋は、4階建てで広大な土地を使用して造られた寮の、最上階の角部屋。目の前には公園の緑が広がる、静かな部屋だった。
窓の外の風景は、暗く霞み、降り注ぐ雨で遠くの空は黒い。目の前の木々の葉からは雫がぽたぽたと落ちていて、この雨は1日中止まないであろうことを予想させた。
今日の部活は人が集まらないな。
雨の日は、道場に人が集まりにくい。ジョギングに当てられる時間がすべて筋トレに回され、そのメニューがきついからだ。
神田はカーテンを閉めると、制服に着替えた。胴着をバッグに詰め、部屋を出る。
時刻は、早朝5時だ。
階段を降りて、玄関口に向かう。神田の部屋は、男子寮の一番奥なので、当然玄関口からは一番遠い。しかし、早朝のこと。誰にも出会うことはないし、とても静かだった。それは、この寮に入った5年前から、変わらない光景だ。
だがしかし、玄関を出たところで、神田は人影を見た。
玄関から門の間には、ささやかな庭が設けられている。その隅、ひときわ大きな木が植えられているその足元で、青い傘を差した人物が座り込んでいた。
こんな早朝になにをしているのか。普段なら無視をして通り過ぎるところだが、時間が時間だ。不審に思った神田は、青い傘に向かって声をかけた。
「おい。こんなところで、なにしてる」
と、青い傘が驚いたようにこちらを振り向いた。その人物を見て、神田も少し驚いた。
最近、やたらラビにひっついて自分の前に姿を現す編入生。
アレンは、本当に驚いた様子で、少し目を泳がせた。そして、顔だけこちらに向けた状態で微笑んだ。
「おはようごさいます、神田。もう学校に行かれるんですか?」
その不自然な様子に、神田は一歩アレンに近づいた。反射的に、アレンは一瞬身体を強張らせる。そして、チラと腕時計を見た。その時、小さく舌打ちが聞こえたような気がした。
「いつも、早くに起きてジョギングをしているそうですね。今日は雨だから、学校でトレーニングですか?」
続けようとするアレンを遮って、神田は口を開いた。
「後ろに、何か隠しているだろう」
アレンは、目に見えて動揺した。「ええと……」となにか言おうとするアレンの後ろから、「クウン……」とか細い犬の鳴き声がして、神田は眉を顰める。
「……犬か……」
この寮では、当然ペットを飼うことはできない。学園内に迷い込んだ野良犬や野良猫は、保健所行きと決まっていた。
アレンは溜息をひとつ漏らすと、後ろに抱えていた犬ごとこちらに向き直った。「静にしてなきゃ駄目だろ」と犬に言いながら、立ち上がる。見たところ、生まれて間もないであろうと思われるほどの仔犬で、毛並みが黄色がかっている雑種だった。その犬の足には、包帯が巻かれていた。怪我をしているらしい。
「3日前に、学校から帰ってきた時にここで見つけたんです。こんなに小さくて、痩せてるのに足を怪我していて、お腹も空かせていて…」
「それで、隠れて世話をしていたわけか」
ふうっと溜息を漏らしながら、神田。アレンは、困ったように仔犬を見下ろした。
その姿に、神田の心が小さくざわめく。こんな姿に、遠い昔覚えがあった。
なんにしろ、神田にはなんの関係もない、どうでもいいことだ。学校に向かわなければ、トレーニングの時間が短くなる。神田は黙って踵を返した。
「あの、神田」
3つの年下の中坊のくせに呼び捨てで呼んでくることに苛ついたので、文句を言うつもりで振り向いた。が、仔犬を抱いたアレンの表情に、その勢いが削がれた。
胸に抱いた、捨てたれた仔犬と同じ目をしたアレンが、こちらを見ていた。
「黙っていてくれませんか、この仔犬のこと……」
そんな目をして、こんなことを言う。
「……誰に言うってんだよ、わざわざ」
「寮長さんとか、管理人さんとか……」
「あいつらに何か言われたことはあっても、自分から話しかけたことなんかねえよ」
不安な眼差しをしていたアレンの目が和らいだ。安心したように笑う。
「ありがとうございます。今日、皆が起きだしたら、管理人さんにこの子のことを話すつもりなんです。今日みたいな雨の日には、この子には厳しいですから。雨が降り出した音がした時は、慌てて飛び起きましたよ」
眠りながらもそんな些細な音を聞き取るほど眠りが浅いのか、と思ったが、特にコメントを出す必要もない。興味がないからだ。
「……飼わせてくれって言うのか?そんな前例、今までねえよ」
アレンはにっこりと笑って言う。
「大丈夫ですよ。ここの管理人さん、気が小さいんで、うまく言いくるめます」
確かに、ここの管理人は気が小さく、神田が機嫌が悪いときにガラスを割った時など、叱るどころか恐縮していた。入寮した時ににケチをつけられたことがあって(内容は忘れたが)怒鳴りつけたことがトラウマになって、神田に怯えているらしい。
アレンは、どうやら本気でこの仔犬を飼うつもりのようだ。
「……人間が動物を飼う、か。そんなの、人間のエゴで動物の自由を奪うってことじゃねえか」
思わず口をついて出た言葉に、アレンが顔を上げた。静かな目で、こちらを見つめてくる。
「……神田はそう思うんですか?」
「動物を飼ってどうするんだ?自分よりも弱いものを庇護している自分に、優越感を感じるためか?そうして動物を飼って、飽きたらどうするんだ?もし、お前がこいつの前から急に消えざるを得ない状況になったら、こいつはどうなるんだ?」
一度口に出してしまえば止まらない。
神田は、「ペットを飼う」ということが、理解できなかった。
動物を自分のものように扱って、世話をする意味が分からない。自分の子供もろくに育てられない人間もいるというのに。いつかそのペットに飽きて捨てる時が来るのなら、始めから飼わなければいい。
動物を飼う、というのは、自分の寂しさを紛らわせるためにものの言えない動物を自分の支配下に置くという、人間の勝手な行為だ。人間の弱さを埋めるために、動物を利用するということだ。
神田は、そんな風に自分の弱さを認めず、別のもので紛らわせて優越感を補足するという行為が、そんな人間が大嫌いだった。
現に、アレンも先程、捨てられた仔犬のような目をした。
おそらくは無意識だろう。アレンはそんな自分に気付いていない。
そのことに、神田は苛つきを覚え始めていた。
「……放っておけないんですよ。この子は、生まれたばかりで、体力もないのに足を怪我していて、こんなにも弱っています」
「それで死ぬんなら、そいつの運命なんだろうよ。放っておけないからってここまで世話をして、管理人にやっぱり保健所行きにされたらどうするんだ?お前は、その犬に、ただ野たれ死ぬよりも辛い運命を与えたことになる」
「……そんなことにはなりませんよ。僕は必ず、この子を守ります」
お前を守ってやるからな。
昔、どこかで聞いた。しかし、その約束は果たされなかった。
胸が苦しくなる。
「……はっ……お前みたいなモヤシがかよ。笑わせんな」
「モヤシ」と呼ばれたことに、アレンが軽く顔を顰めた。
「……神田は、今何を思い出しているんですか?」
じっとこちらを見据えたアレンの言葉に、自分の身体が一瞬強張るのを感じた。
「あなたは関心がないことは、徹底的に無視するでしょう。僕がこの仔犬を飼おうと飼うまいと、あなたにはどうでもいいことのはずです。なぜ絡むんですか」
一瞬、幼い頃の記憶がフラッシュバックするかと思った。
かろうじでそれを抑えた神田は、今度こそアレンに背中を向けようと、足の向きを変えた。
「興味なんかねえよ。ただ、ここで犬なんか飼われたら鬱陶しいと思っただけだ」
「あなたに迷惑はかけませんよ。……この子を飼う、という行為があなたを苛つかせるというのなら、それだけであなたは迷惑なのかもしれませんが」
……思ったより、いやみったらしく攻撃をしてくる。
ただで立ち去るのは癪で、神田はチラとアレンを見た。
「……そのお優しい一面、動物だけじゃなく人間にも向けてやったらどうだ?」
アレンの目が大きく見開かれた。
「……え?」
今度こそ、神田は寮の門を出た。
学校に着いたのは、いつもよりも30分も遅い時間だった。
「へえ~その犬、アレンが飼うのか?」
「ティムキャンピーって名前をつけたんですよ。みなさんティムって呼んで、可愛がってくださいね」
「へえ~小さくて可愛いなあ」
アレンを取り巻く生徒たちの顔には「仔犬を抱くアレン、萌え!」と大きく書かれている。
結局、仔犬はアレンの思惑通り、寮で飼うこととなった。ただし、アレンの部屋で。犬が苦手な生徒もいるのでむやみに放し飼いにしないこと、世話は一人ですること、が条件だ。一体どんな方法で説得されたのか、管理人であるアレスティーナ(以下略)のアレンを見る目が、明らかに恐怖で怯えていることには、今のところ神田しか気付いていない。
神田が談話室の前を通りかかると、仔犬を抱いたアレンを中心に生徒達が集まって軽いお祭り騒ぎになっていた。これで、アレンの出現によってまたひとつ、この学園での日常が変えられたことになる。
「あ、ユウ!お前も見てみろよ、こいつ、ティムって言うんだぜ」
黙って通り過ぎようとする神田を目ざとく発見したラビが、大きく手を振ってきた。同時に、アレンもこちらに視線を向ける。
立ち上がると、仔犬――ティムを肩に乗せて、ゆっくりと神田の近づいてきた。目の前で立ち止まると、にっこりと笑う。
「はじめまして、ティムです。この子、僕が飼うことになったんですよ。よろしくお願いします」
まるで今朝のことがなかったかのように、ティムを紹介した。
なぜ、こんなにも神田に惹かれるのだろう。
そう思ったことは何度かあった。
まっすぐに前を見て走る、穢れのない美しい姿に心を奪われた。
それだけなら、こんなにも神田に執着することはないと思う。
その理由が、やっと分かった。
神田は心もこんなにもまっすぐで、穢れがない。
ラビに惹かれる理由もそうだ。
アレンは、自分に足りない美しいものを持っている彼らが、愛しい。
だが、神田とラビは違う。決定的に違う。
美しくてまっすぐな君を。
僕でいっぱいにしたい。
--END--