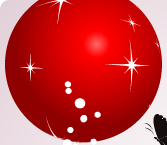「DEAR FRIEND」
母親にお客さんだと言われて訝しげに思いながらも向かった玄関先。3人の若者が陽気にこんばんは~と挨拶をしてきたのを見て、夏野は無言で戸を閉めた。「待って!待って!」と、戸の向こう側から武藤徹の声が聞こえる。
馴れ合う気は、ないのに。
夏野一家が外場に越してきて数日目。
人がこの家を訪ねてきたのは初めてだった。
結局やや強引に家の中に入ってきた武藤徹とその二人の連れは、結城・小出家の居間でにこにこと夏野と向かい合っていた。もっとも、夏野は雑誌に夢中になっているフリをしていて、彼らを見ようともしていないのだが。
「じゃ、とりあえず自己紹介!」
かなり気まずい空気が流れているのをものともせず、武藤徹が明るい声をあげた。
「おれは武藤徹、19歳!会社員やってます」
続いて隣に座った明るい色の髪の少女がにっこりと笑った。
「武藤葵、17歳。商業高校2年生です」
さらにその隣の、葵と似た髪質をした少年が人懐こく笑う。
「武藤保。16歳高校1年です」
そして3人はこっそり「せ~の」とタイミングを合わせ
「どうぞよろしく~」
と声を合わせて笑った。
「…………」
自己紹介をされた夏野は無言で雑誌のページをめくる。
しばしの無言状態。
葵が徹の耳を引っ張り、ひそひそと抗議の声を上げた
。 「ちょっと!どういうことよ赤るいノリでいったら大丈夫って言ったじゃない!」
保も応戦する。
「すげえクールで人見知りじゃないか!聞いてねえよ!」
(……別に人見知りでもないけど)
ガキじゃあるまいし、と夏野はどうやら兄弟である3人のまる聞こえの内緒話を聞くともなく聞いていた。
こんな村で友達を作る気はない。
無視し続けていたらそのうち帰るだろう、と雑誌に気を向けると、居間の襖が開いて、母親の梓がジュースのグラスを乗せた盆を持って入ってきた。
「いっらしゃい。ゆっくりしていってね」
にっこりと笑った梓の顔を見た葵が、思わず夏野に声をかけた。
「ってうか、お母さん若くない?」
物怖じしない娘らしい。夏野は葵ちらりと見たが、何も言わずに再び雑誌に目を落とした。両親が若いことで、いろいろと苦労をしてきた。コメントをしたくなかった。
梓の後ろから父親までも顔を出す。その若さに3人が軽く驚いた空気を感じたが、夏野は無視した。
「やあいらっしゃい。夏野にもう友達ができたとは驚いたな」
田舎の情緒に憧れる父親が嬉しそうに言うのを、夏野は冷めた気分で聞いていた。友達じゃないし、と思ったが、ここでそれを口にすると面倒なことになるし、そんな子供っぽいことをしたいとも思わなかった。
徹が両親と柔らかな物腰で挨拶を交わし、軽い世間話を始める。自分と5つしか変わらないのに世間慣れした様子に夏野は徹を盗み見た。初めて道路で会った時も感じたが、彼は初対面の人間にも警戒心を抱かせない、暖かい雰囲気を纏っていた。
横に並ぶ葵と保も、人懐こい様子を感じるが、いかにも活発そうで、なるほどこんな妹弟を持つ兄に徹は相応しい。
「ところで二人の格好。今日は祭りでもあるのかい?」
葵と保はそれぞれ浴衣を着ている。徹はごく普通のシャツにジーンズだ。……ややダサイが。それに応えて葵がひょいと袖口を持ち上げた。
「お祭りがあるんです。それで、夏野くんを誘いにきたんです」
冗談じゃない、そんなところに行ったら晒し者もいいとこだ、と思ったが、「へえ……」という父親の声に、ああこれは行くことになるな、と夏野は肩を落とした。
■
「行かないっつったのに……」
ささやかな屋台が並ぶ祭り会場を徹と並んで歩きながら、夏野はため息をついた。
いかにも田舎の村らしく、結束感のあるささやかながらはりきった祭りだ。徹が言うにはこの後、「虫送り」という、見てはならない行事があるらしい。観客がいないのならやる必要がないのではないか、と思うのだが。理解できない。
「いいじゃないか。親父さん、お前に友達ができたってよろこんでたし」
「親父喜ばせてどうすんだよ……」
夏野が大仰にため息をつくと、屋台を覗いていた葵と保が猫なで声を出しながら徹に擦り寄った。
「兄貴~社会人!あたし、りんごあめが食べたいな~」
「おれ焼きそばが食いたいかも~」
「……お前ら、もしかしておれをあてにして財布持ってきてないのか……?」
情けない顔をしながらしかし、徹は財布から金を出して二人に渡した。葵がサンキューと嬉しそうに屋台に走るのに、保が続く。
なんとなくこの兄弟の上下関係が見えた気がした。
「……なに?」
気付くと徹をじっと見つめていたらしい。夏野は、徹の持つ財布をちらりと見る。
「……あんた、社会人なんだよな」
徹は、合点がいったように軽く笑った。その柔らかな笑顔に、夏野は少しだけ心臓が踊るのを感じる。都会にいた頃は、こんな笑顔をする人をあまり見なかった気がする。
「ああ。村から溝辺の会社に通ってる」
「……ふーん……」
なんとなく面白くない気分になった夏野は、はっきりと拒絶の空気を出しながら徹の隣を離れた。ぽそりと呟いて、3人から離れるように歩き出した。
「おれなら出るな、ここ」
引っ越すことになった、と言った時のあちらの友人の反応を思い出す。
外場村に初めて下見に来た時の驚きと絶望を思い出す。
電車すらない村だ。そんな場所があることさえ、都会にいる時は忘れていた。
夏野は祭り会場から離れるように、木々に間を縫って神社から離れた。
少し離れただけで、喧騒や明かりが木々に遮られて静かで暗い空気に包まれる。
こんなに木がたくさんある場所なんて、長時間電車に揺られないと行くことができなかった。
夜がこんなに静かで暗くなるなんて、都会ではもっと遅い時間のこと、下手をすれば一晩中だって賑わっていた。
唐突に、自分は違う世界に来てしまったのだという思いに駆られた。
この村の夜は、こんなにも暗い。
歩いていると、木々が途切れた、少し開いた場所に出て、村と山を見下ろせる場所に出た。
かつて見た、明るい光を散りばめたような、ビルの並ぶ夜景が脳裏を掠めたが、実際に見えたのは、ただただ飲まれるように暗い景色だった。
「……お前ら知ってるのかよ」
この暗闇の中に生きる、村人たち。
この村に生息する山、木、動物たち。
「夜は人間の時間だってこと」
呟いた瞬間、すぐそばの空で大きな音を立てて花火が散った。瞬間、空が明るくなり、離れた祭り会場から歓声が聞こえた。
こんなに近くで花火を見たのは初めてで、夏野は声を出すのも忘れて花火を見上げた。
「今の台詞ってさ、祭りの夜に言うことじゃないよな」
背後から徹の声がして、夏野はさっと振り向いた。先ほど夏野が通ってきたあたりの木のひとつにもたれ掛かり、徹は微笑を浮かべて夏野を見ていた。
またひとつ花火が上がる。
二人はしばし、見つめ合っていた。
にっこりと徹が笑い、手に持った袋を差し出してきた。
「たこ焼き。食うだろ?買いすぎたから1パック。ノルマな」
急に気が抜けた夏野に構わず、徹はたこ焼きが12個入ったパックをひとつ開けて、ご丁寧に爪楊枝をセッティングして夏野に押し付けてきた。
「……こんなに食えるかよ」
「いいだろ。儀式だよ、儀式」
なんのだよ、とたこ焼きをひとつ、口に入れる。思ったよりもおいしかった。
「……夜ってさ、いつも明るいのもいいけど、こうやってたまに明るい日があると、楽しみも倍増って感じ、しないか?葵も保も、テンション高いし」
「……そんなもんかな」
都会よりも少し冷える空気の中、暖かいたこ焼きが妙にうまいことが悔しい。暗いこの村の中で、徹の笑顔が明るい。
真っ暗な空に、また新しい花火が咲き、散った。
「……おれ、ここ出るよ」
花火のように。大きく花開けば、この村から飛び出せる。飛び出した空はあの街に繋がっている。
あの街に、自分の居場所に戻ってみせる。
そのためならどんな努力だってしてみせよう。
その呟きが聞こえたのか聞こえなかったのか、徹は陽気な声を上げて空を見上げた。
「ここ特等席だな~、花火すげえよく見える」
「……ていうか、なに勝手に隣で見てるわけ」
仏頂面で見上げると、徹はあの笑顔で笑った。
「たこ焼きやったんだから、いいだろ」
気がつけば手の中のパックは、空になっていた。
■
葵と保の元に戻ると、保が同年代らしい少年となにか言い合ってた。
「なんで勝手に祭り来てるんだよ。一緒に行こうって約束してたから、おれ、待ってたんだぜ」
「どうせ来るんだろうからこっちで見つければいいと思ったんだよ」
「はあ?それじゃ約束したことにならなくね?」
どうやら、別の友達と約束していたところ、保は相手ほど深く考えずに夏野を誘ってしまったので、それを責められているらしい。
保と言い合っている少年は、いかにも我侭を言いそうな、一人っ子か末っ子かという印象を与える容姿をしていた。
そばで困ったように2人を見ていた葵に徹が声をかける。
「葵、どうした?」
「あ、兄貴……」
「徹ちゃん!」
葵が何か言う前に、当の少年が声を上げて徹に駆け寄り、ふと夏野を見た。
「誰それ」
今日までに何度も見てきた、余所者を排斥しようという目だ。
そんな少年の様子に目もくれず、徹は楽しそうに笑って夏野の肩を抱いてきた。
「村に越してきた結城?小出?まあどちでもいいや、夏野くんだ!せっかくだから祭りに誘ったんだ。夏野、こいつは保の幼馴染で村越正雄」
「……名前で呼ばないでくれる」
「え、なんで?」
「おい!」
正雄よりも夏野に構いだした徹に、正雄が苛立ったように詰め寄った。
「約束してたおれより、新参者の余所者を優先したのかよ!2週間も前から約束してたおれより!」
言ってることの子供っぽさに、夏野は呆れた。保と幼馴染ということは、自分より1つ年上なのだろうが、言ってることがあまりに幼い。
ふと見ると、葵が困った顔で正雄の様子を伺っていた。
(ふ~ん……)
「くっだらね」
言うと、正雄が顔を赤くして夏野を睨んだ。
「なんだお前、新参者が」
「あんた小学生?約束してたのなんだのって、1人じゃ外にも出れないわけ?結果的にここで会えたんだからいいじゃないか」
「なんだと?お前年下だろ?年上に向かって生意気じゃないか?」
「1つか2つの違いだろ。くだらねえ」
「なんだと!?」
2人の口喧嘩を(正確には正雄の一歩意的な)少し離れたところで眺めていた武藤兄弟は、揃ってどっちが年上だか分からないな、と思っていた。
「う~ん派手に始まったなあ」
「どう見ても正雄の負けだけどな」
「じゃなくて!二人とも正雄くんを止めてよ!」
仕方なく止めに入ると、夏野が最初から相手にしねえよこんなやつ、と言うのに正雄が更に切れ、徹が夏野を庇うものだから、正雄は保に押さえつけられるような形になった。
遠巻きに村人達の観客が集まる中、夏野はこの村に来て初めて自分らしい調子を取り戻していた。
(こんな村でも何かいいこともあるかもしれないぜ)
あるのかもしれないし、ないのかもしれない。
でも今日は、あんたに誘ってもらえてよかった。
これからどうするべきなのか、道しるべができた。
拗ねてる場合ではない。
少しずつでいい、村を出る準備を進めるのだ。
そう決心できたのは、あの時あそこで一緒に花火を見たから。
ありがとう、徹ちゃん。
--END--